COLUMN コラム
電子マニフェストとは?メリット・デメリットや紙マニフェストとの違いを比較!

産業廃棄物の適正処理には「マニフェスト」という仕組みがあり、これは紙マニフェストと電子マニフェストの2種類に分かれます。電子マニフェストを利用すると、事務作業の負担が軽減されるほか、法令順守がしやすくなるといったメリットがあります。
しかし「紙と何が違うのか」「どこが優れているのか」が分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
本記事では、電子マニフェストの概要やメリット・デメリットを紹介しています。また、紙のマニフェストとの違いも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
電子マニフェストとは?
電子マニフェストとは、これまで紙で行っていた発行・報告・管理の業務をオンラインで行える仕組みです。
電子マニフェストを使うと、排出事業者・収集運搬業者・処分業者が、廃棄物の運搬や処理状況をリアルタイムで確認できます。これにより、業務の効率化や法令順守の強化が期待できます。
マニフェスト制度は、当初は紙による交付から始まりました。その後、1998年にインターネットを活用した電子マニフェストが登場し、しばらくは紙と電子のどちらかで交付するルールが続いていました。
しかし、2020年4月以降、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の排出事業者は、電子マニフェストの加入が義務化されました。これに違反すると罰則が科されるため、該当する事業者は必ず電子マニフェストを導入する必要があります。
2023年時点で普及率は81%に達しており、今後さらに広がる見込みです。
出典:環境省「電子マニフェスト使用の一部義務化等について」(https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/faq_mani.html)
マニフェスト制度
マニフェストは、正式には「産業廃棄物管理票」といい、産業廃棄物の適正な処理を管理するための制度です。
排出事業者は、産業廃棄物を収集運搬業者や処分業者に委託する際にマニフェストを発行し、適正に処理されたことを確認・記録します。排出から最終処分までの流れを明確にすることで、不法投棄や不適正処理を防ぐことが目的です。
かつては産業廃棄物の処理状況を把握する仕組みがなく、不法投棄やずさんな処理が問題となっていました。こうした課題を解決するため、1990年の廃棄物処理法改正により、マニフェスト制度が導入されました。
マニフェスト制度は、基本的にすべての排出事業者が対象ですが、国や地方公共団体に委託する場合や、再生利用目的で特定の業者(専ら業者)に委託する場合は、例外として義務が免除されます。
紙のマニフェストを使用している場合、排出事業者は前年度の使用状況を都道府県へ報告する義務があります。一方、電子マニフェストなら、日本産業廃棄物処理振興センターのJWNET(電子マニフェストシステム)にデータを登録することで、報告が自動で完了します。
イーブライトでは、企業から排出される廃棄物の収集・分別・リサイクルを行っております。電子マニフェストの対応も可能なため、ぜひ一度ご覧ください。
電子マニフェストの導入メリット
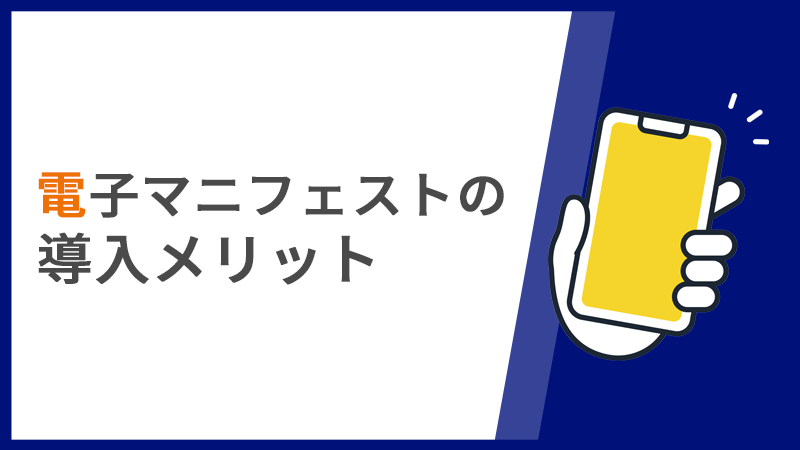
電子マニフェストは、産業廃棄物の管理をデジタル化することで、業務の効率化や法令遵守の強化につながるツールです。ここでは、電子マニフェストの導入メリットについて紹介します。
処理状況をリアルタイムで確認可能
従来の紙マニフェストでは、収集運搬業者や処分業者から書類が返送されるまで、排出事業者は廃棄物の処理状況を把握しにくいという問題がありました。しかし、電子マニフェストを導入すると、産業廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認できます。
収集運搬業者や処分業者が作業完了後、インターネット上で処理状況を報告するため、紙マニフェストのように伝票の返送を待つ必要がありません。JWNETにアクセスすれば「現在どの処理段階なのか」「どの業者が対応しているのか」をすぐに確認できます。
排出事業者には委託した業者が適切に処理しているかを確認する義務があるため、リアルタイムで状況を把握できるのは大きな安心材料となります。
廃棄物の排出・処理委託情報を簡単に把握できる
紙マニフェストでは、必要な書類を見つけるために、バインダーやファイルを1枚ずつ確認する必要があり、時間も手間もかかります。一方、電子マニフェストを導入すれば、廃棄物の排出や処理の委託情報を簡単に把握できます。
JWNETにアクセスするだけで、必要な情報をすぐに確認可能です。過去のデータも検索するだけで見つかり、データはダウンロードできるので、集計や分析もスムーズに行えます。
マニフェストの紙保存が不要になる
紙のマニフェストは5年間の保管義務があるため、管理の手間や紛失のリスク、収納スペースの確保が課題となります。一方、電子マニフェストは、マニフェストの情報をシステム上に保存できるため、紙の保管が不要です。
データはインターネット上で一括管理でき、紛失の心配がありません。業者からの完了報告もメール通知で受け取れるため、確認作業がスムーズになります。紙のように大量の書類を保管するスペースを確保する必要もありません。
また、紙のマニフェストは、処理の進行に応じて1枚ずつ返送されるため、管理が複雑になりがちです。とくに多くの産業廃棄物を排出する事業者では、膨大な紙のマニフェストを整理する手間がかかり、必要な書類を探すのに時間を要します。
万が一紛失すると、法令違反につながるリスクもあります。電子マニフェストを導入すれば、紙の保管義務がなくなり、管理負担を軽減できるのがメリットです。
産業廃棄物管理票交付等状況報告の負担が軽減される
電子マニフェストを利用すると、産業廃棄物管理票交付等状況報告の負担を軽減できます。産業廃棄物を排出する事業者には、毎年、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する義務があります。
この報告は、マニフェストの運用状況を自治体へ知らせるもので、過去1年分の交付枚数や処理状況などのデータを集計し、提出しなければなりません。
しかし、電子マニフェストを導入すれば、この報告作業は不要になります。JWNETのシステムを通じてデータが自動で集計・報告されるため、排出事業者が個別に報告書を作成する手間がなくなります。
ただし、紙マニフェストを併用している場合は、紙マニフェスト分の報告が必要です。業務の効率化を図るためには、電子マニフェストへの一本化が推奨されます。
入力ミスや作業ミスを防止できる
電子マニフェストは、システムが記入項目を自動でチェックしてくれるため、入力ミスや作業ミスを防げます。一方、紙のマニフェストは、手書きによる記入ミスや誤りなどのヒューマンエラーを起こしやすいのが難点です。
どれほど注意していても、誤記や記入漏れが起こる可能性があり、その分だけ修正作業の負担も大きくなります。
また、マニフェストには法定記載事項が定められており、誤記や記入漏れがあると罰則の対象となる可能性があります。単なるミスでは済まされないため、正確な記入を心がけなければなりません。
電子マニフェストなら、法定記載事項の部分が赤字で表示されるため、記入漏れを未然に防げます。法令違反のリスクを抑えながら、業務の効率化も実現できます。
事務作業の効率化が図れる
電子マニフェストを導入すると、事務作業が効率化されるため、日々の業務負担を軽減できます。従来の紙のマニフェストは、手書きのため、誤字や脱字、記入漏れが発生しやすく、修正にも手間がかかるのが難点です。
さらに、廃棄物を渡すと同時にマニフェストを記載・交付する必要があります。作業完了報告も、収集運搬業者や処理業者からの郵送を待たなければなりません。
電子マニフェストなら、廃棄物を引き渡した後、3日以内にシステムへ登録すればよいため、事務作業に余裕が生まれます。データを直接入力できるため、記入ミスを防ぎやすく、修正も簡単です。
また、オンライン上で収集運搬業者や処理業者とデータを共有できるため、郵送やファイリングの手間が不要になります。自治体への1年間の報告業務も自動化されるため、不要です。
法令遵守を徹底される
産業廃棄物を適切に処理するには、マニフェストを正しく運用することが欠かせません。電子マニフェストを導入すれば、リアルタイムで処理状況を確認できるため、法令遵守を強化できます。
一方、紙のマニフェストは管理が煩雑なため、ヒューマンエラーが発生しやすく、不正やトラブルの発見が遅れるリスクがあります。不適正処理や不法投棄につながる可能性があるのが問題です。
電子マニフェストなら、インターネット上でデータを一元管理でき、最新の処理状況を即座に把握可能です。排出事業者・収集運搬業者・処理業者がデータを共有することで、監視体制も強化されます。修正があった場合も、相手に通知が届くため、データの改ざんリスクを抑えられます。
環境負荷を低減できる
電子マニフェストを導入すれば、ペーパーレス化により環境負荷の軽減が可能です。紙のマニフェストは、7枚複写式の専用伝票を使用し、産業廃棄物の種類ごとに多くの紙を消費します。結果として、森林伐採が進み、廃棄後の焼却によるCO₂排出も増えます。
電子マニフェストなら、すべてのデータをオンラインで管理できるため、紙の消費を削減できます。紙の製造や焼却にともなうCO₂排出を抑え、環境保護にも貢献できます。
電子マニフェストの導入デメリット
電子マニフェストは業務の効率化に役立つ一方で、システム障害のリスクや全関係者のJWNET加入が必要などの課題もあります。導入を検討する際は、以下の点を十分に理解し、慎重に判断しましょう。
インターネット環境が必須となる
電子マニフェストは、JWNETのオンラインシステムを利用してデータを管理・送信するため、インターネット環境が必要不可欠となります。そのため、導入時には以下のようなコストや準備が必要になる場合があります。
・インターネット回線の契約や導入費用
・パソコンやタブレットの購入費用(既存の端末がない場合)
電子マニフェストは、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも利用できます。そのため、外出先や現場でも産業廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認できるのがメリットです。対象機器や利用環境については、JWNETのホームページで確認ください。
導入に費用がかかる
電子マニフェストを導入する際は、JWNETの登録・利用にともなう費用が発生します。排出事業者は、マニフェストの登録件数に応じて、A料金・B料金・C料金の3つの区分から選択できます。
料金区分の違い(A料金・B料金・C料金)
| 料金区分 | 対象者 | 基本料(年間) | 使用料(1件あたり) | 無料登録件数 | 特徴 |
| A料金 | 大量のマニフェストを登録する排出事業者向け | 26,400円 | 11円 | なし | 登録件数が2,401件以上になる場合にお得 |
| B料金 | 少量のマニフェストを登録する排出事業者向け | 1,980円 | 91件目から22円 | 90件まで無料 | 登録件数が2,400件以下ならA料金よりお得 |
| C料金(団体加入) | マニフェスト登録が少ない小規模事業者向け | 110円 | 6件目から22円 | 5件まで無料 | 20者以上の団体加入が必要、利用代表者を通じて加入できる(排出事業者が直接手続きすることはない) |
出典:JWNET「利用料金」(https://www.jwnet.or.jp/jwnet/youshiki/payment/fee/index.html)
業務が複雑になるおそれがある
電子マニフェスト未加入の業者と取引する場合、一部を紙のマニフェストで管理する必要が出てきます。しかし、電子と紙が混在すると業務が複雑になり、全体の状況を把握しにくくなるのが課題です。
また、紙のマニフェストは手作業が多いため、事務作業の負担が増えます。手書きによる発行は業務効率を下げるだけでなく、記入漏れや紛失のリスクも高めます。こうした問題を防ぎ、業務をスムーズに進めるためにも、電子マニフェストへの統一が望まれます。
関係する全事業者の電子マニフェスト加入が必要となる
電子マニフェストを利用するには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のすべてがJWNETへ加入していなければなりません。データのやり取りはJWNETを通じて行われるため、どれか1社でも未加入の場合、電子マニフェストの運用はできません。
また、未加入の業者が新たに加入するには時間がかかることがあり、その間は紙のマニフェストを使用せざるを得ない場合があります。加入手続きの完了だけでなく、従業員への教育、電子管理に対応する業務フローの見直しなどが必要になるためです。
とくにIT環境が整っていない企業では、ネット回線やパソコンの導入から始める必要があり、電子化の準備に時間を要することもあります。
システム障害発生時のリスクがある
電子マニフェストはオンラインシステムを利用するため、システム障害が発生すると一時的に使用できなくなるリスクがあります。アクセスの集中によるシステムダウンやエラーが起こると、マニフェストの登録・確認・更新ができなくなります。
そのため、新たな廃棄物の処理手続きを進められず業務が滞る可能性は否めません。障害が長引く場合は、復旧までの間、一時的に紙のマニフェストで対応しなければならない可能性があります。
また、近年は情報漏洩や不正アクセスのリスクも高まっており、セキュリティ対策が不可欠です。電子マニフェストを安全に運用するためには、適切な管理体制を整え、透明性を確保することが求められます。
電子マニフェストと紙マニフェストとの違い
自社に適したマニフェストを運用するには、紙と電子のマニフェストの違いを正しく理解することが大切です。ここでは、発行や報告の方法、運用の流れ、義務の面からの違いを解説します。
運用方法
紙のマニフェストは、産業廃棄物と一緒に移動しながら運用される仕組みです。各業者や排出事業者が必要な伝票を5年間保管することで、不適切な処理や不法投棄を防ぎます。
運用の流れは以下のとおりです。
1.排出事業者がマニフェストを作成(7枚複写の伝票)
廃棄物を運搬業者に引き渡す際、同時に手渡します。
2.運搬業者が廃棄物を運搬
作業完了後、B2票が排出事業者に返送されます。
3.中間処理業者が処分を実施
処理完了後、D票が排出事業者に返送されます。
4.最終処分業者が処理を完了
最後にE票(最終処分完了の証明)が排出事業者に届きます。
排出事業者は、運搬終了・処分終了・最終処分終了ごとに、伝票(B2票・D票・E票)とA票を照らし合わせ、すべての処理が適正に行われたか確認しなければなりません。
一方、電子マニフェストは、紙のやり取りをなくし、すべてをオンラインで管理できる仕組みです。排出事業者は、廃棄物を引き渡してから専用システム(JWNET)にデータを登録します。処理が完了すると、システムから自動通知が届くため、画面上で運搬・処理・最終処分が終わったかをリアルタイムで確認可能です。
発行・報告のタイミング
紙のマニフェストは、廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に、同時に発行する必要があります。一方、電子マニフェストは、引き渡しの際に即時登録する必要はなく、土日・祝日を除いた3日以内にJWNETへ登録すれば問題ありません。また、廃棄物を渡した日は、この3日間には含まれません。
処理終了報告については、紙のマニフェストでは、収集運搬業者や処分業者は作業完了後10日以内にマニフェストを排出事業者へ送付する必要があります。電子マニフェストの場合は、収集運搬業者や処分業者が作業完了後3日以内にJWNETへ報告を入力することで処理が完了します。
義務
紙のマニフェストでは、排出事業者に5年間のマニフェストの保管義務があります。また、年に1回、都道府県へマニフェストの使用状況を報告しなければなりません。
一方、電子マニフェストを利用すれば、報告は情報処理センターが代行します。排出事業者の報告義務はなく、保管義務もありません。
こちらの記事では、電子マニフェストの流れについて解説しています。導入する際の注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
電子マニフェストと紙マニフェストどっちがよい?
電子と紙マニフェストは、それぞれメリットとデメリットがあります。ここでは、業務効率の向上や導入時のハードルの低さといった観点から、それぞれのおすすめのケースを詳しく解説します。
業務効率の向上は電子マニフェスト
業務効率の面では、紙よりも電子マニフェストのほうが優れています。オンライン上の管理により、事務作業の負担を軽減できるからです。
紙のマニフェストでは、戻ってきた伝票を都度確認し、廃棄物を引き渡した際に業者に記入してもらう必要があります。また、伝票の紛失リスクや記入ミス・漏れが発生しやすく、年に1回、行政へ使用状況を報告する義務もあります。
一方、電子マニフェストはオンライン上で一括管理できるため、紛失の心配がなく、手書き作業や伝票の確認にかかる負担も軽減可能です。
また、入力漏れを防ぐシステム設計により、法定記載事項の記入ミスを防止でき、年に1回の行政報告も不要になります。書類作成や確認、整理の手間が減ることで、人的リソースの削減にもつながるでしょう。
導入時のハードルの低さは紙マニフェスト
導入のしやすさは紙マニフェストの方が有利です。紙マニフェストは、専用の伝票を購入し、手書きで記入するだけで運用を開始できます。
一方、電子マニフェストを導入するには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のすべてがJWNETに加入しなければなりません。システムの利用料が発生するほか、従業員の操作研修やIT環境の整備、セキュリティ対策などの準備が必要となるため、導入時の負担は大きくなります。
ただし、紙マニフェストは管理や運用に手間がかかるため、長期的に見ると電子マニフェストのほうが業務の効率化や法令遵守の面で有利です。マニフェストの管理が複雑になるほど、電子化によるメリットはより大きくなります。
電子マニフェストと紙マニフェストの併用はあり?
電子マニフェストと紙マニフェストを合わせて利用すると、管理が複雑になります。異なる形式のマニフェストを同時に扱うと、情報をまとめて管理できず、確認作業が増えて事務負担が大きくなるためです。そのため、できるだけ電子マニフェストに統一するのが理想的です。
ただし、小規模な処理業者のなかには電子マニフェストに対応していないところもあります。その場合は、紙マニフェストを一部併用するか、電子マニフェストに対応している処理業者を検討するのもひとつの方法です。
イーブライトでは、紙マニフェストだけでなく、電子マニフェストにも対応可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
電子マニフェストは、産業廃棄物の処理状況をインターネット上で管理できるシステムです。紙マニフェストに比べて、処理状況をリアルタイムで確認できることや、報告の自動化による業務効率化と法令遵守の強化が期待できます。また、ペーパーレス化により保管スペースや紛失リスクが削減され、環境負荷の低減にも貢献します。
一方で、導入にはインターネット環境やシステム利用料が必要であり、電子マニフェスト未対応の業者と取引する場合は紙と電子の併用による管理の煩雑さが課題となります。
もし、マニフェストに関する疑問や不安があれば、イーブライトにお任せください。イーブライトでは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・静岡県で収集・分別・リサイクルを行っています。
紙マニフェストはもちろん、電子マニフェストにも対応しており、効率的な管理方法で運搬・処理が可能です。また、計量器付きパッカー車を導入することで排出量管理や処分費用の明確化を実現しています。
廃棄物についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。




