COLUMN コラム
流行る飲食店コンセプトの決め方!誰でもできる5W2Hの思考法を解説

飲食店を開業する際「自分の想いをどう形にすればいいのか」「コンセプトって具体的に何を決めればいいの?」と悩んでいませんか?実は、明確なコンセプトこそが飲食店成功の鍵を握っています。
本記事では、誰でも実践できる5W2Hの思考法を使って、具体的なコンセプトに落とし込む方法を解説します。
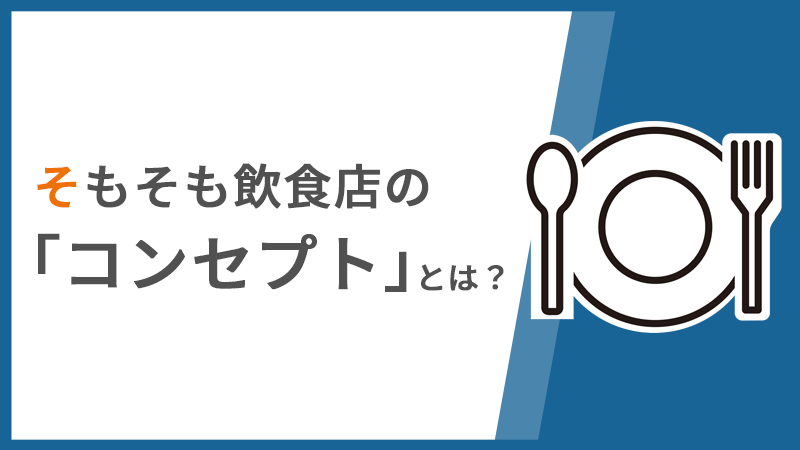
そもそも飲食店の「コンセプト」とは?
飲食店のコンセプトとは、お店が提供する価値や方向性を示し、すべての判断の軸となるものです。簡単に言えば「なぜこのお店が存在するのか」「どんな価値を提供したいのか」を明確に言語化したものです。
たとえば「毎日通いたくなる町の定食屋」というコンセプトなら、メニューは日替わりで飽きない工夫をし、価格は手頃に設定し、接客は親しみやすくする、というようにすべての要素がこのコンセプトから導き出されます。
なぜ飲食店でコンセプトが重要なのか
コンセプトが重要な理由は大きく2つあります。
ひとつ目は「競合との差別化」です。今や飲食店は全国に約100万店舗存在すると言われ、ただ「美味しい料理を提供する」だけでは選ばれません。明確なコンセプトがあることで「あの店は〇〇だから行く」という選ばれる理由が生まれます。
もうひとつは「経営判断のブレ防止」です。飲食店経営では日々さまざまな決断を迫られます。新メニューの開発、価格改定、内装のリニューアル、スタッフの採用基準など、判断に迷う場面は数えきれません。
そんなとき、明確なコンセプトがあれば「このコンセプトに合っているか」という一貫した判断基準で決定できます。
飲食店でコンセプトが反映されるのはどういうところ?
抽象的になりがちなコンセプトですが、実際にはお店のあらゆる要素に具体的に反映されます。ここでは、コンセプトが形となって現れる主要な要素を見ていきましょう。
店名
店名は、顧客が最初に接するお店の顔です。コンセプトを端的に表現する重要な要素であり、第一印象を大きく左右します。
たとえば、ひらがなは親しみやすさや温かみを感じさせ、家庭的なコンセプトと相性がよいです。一方で漢字は、格式や伝統を感じさせます。ローマ字表記は、洗練されたイメージやグローバル感を演出できます。
店名に込める意味も重要です。たとえば、地域の特産品や食材の名前を取り入れることで、土地への愛着やこだわりを伝えられます。また、ポジティブなイメージを持つ言葉を選ぶと、覚えやすさや口コミの広がりやすさにつながります。
内外装
内外装は、コンセプトを五感で体験してもらう空間演出の要です。
たとえば「落ち着いた大人の隠れ家」というコンセプトなら、照明は間接照明で落ち着いた雰囲気を演出し、BGMはジャズやクラシックを控えめな音量で流し、客席間隔を広めに取ってプライバシーを確保します。
逆に「活気あふれる下町の大衆酒場」なら、明るい照明、にぎやかなBGM、カウンターや相席もある密度の高い配置など、まったく異なる空間設計になります。
また、素材選びも重要です。木材を多用すれば温かみのある雰囲気に、コンクリートや鉄を使えばインダストリアルでモダンな印象になります。これらすべてがコンセプトと一致していることで、強い印象を残せるのです。
接客スタイル
接客スタイルは、顧客との直接的な接点であり、コンセプトを人を通して伝える重要な要素です。
たとえば、高級フレンチレストランなら、ソムリエが料理に合うワインを提案し、一皿ごとに丁寧な説明を加える接客が求められます。一方、ファストフード店なら、効率的でスピーディーな対応が重要になります。
また、接客用語やユニフォームも同様です。カジュアルな店ならTシャツとエプロン、フォーマルな店なら黒服にネクタイなど、視覚的にもコンセプトを表現できます。
メニュー
メニューは、コンセプトを味覚で表現するもっとも直接的な要素です。料理の内容はもちろん、品数、ポーション、価格、見た目のすべてがコンセプトと連動します。
たとえば「働く女性の健康を支える」というコンセプトなら、野菜中心で彩り豊かな料理、カロリー表示、小盛りオプションなどが考えられます。「がっつり食べたい学生のための店」なら、ボリューム重視、肉や炭水化物中心、追加トッピング無料サービスなどが適しています。
また、メニューの数も重要です。専門店なら少数精鋭で深く、ファミリーレストランなら幅広いラインナップで、それぞれのコンセプトに応じた構成になります。
価格設定も同様で、ターゲット層の経済力、利用シーン、提供価値に見合った設定が必要です。安さだけを追求するのではなく、コンセプトに合った「適正価格」を見つけることが大切です。
飲食店のコンセプト設計は5W2Hで考える!
ここからは、実際にコンセプトを作る具体的な方法を解説します。
5W2Hとは、Why(なぜ)、Who(誰に)、What(何を)、Where(どこで)、When(いつ)、How(どのように)、How much(いくらで)の7つの視点から物事を考える方法です。これを順番に埋めていくことで、自然とコンセプトの全体像が見えてきます。
【Why】なぜ
最初に考えるべきは「なぜこの店を開きたいのか」という根本的な動機です。これがすべての土台となり、ブレない軸になります。
「地元の食材の素晴らしさを伝えたい」「忙しい現代人に癒しの時間を提供したい」「故郷の味を都会で再現したい」など、あなたの情熱を言語化してみましょう。
ここで大切なのは、社会的な意義や顧客への価値だけでなく、自身の想いも含めることです。「自分が子どもの頃に感動した料理を多くの人に届けたい」といった個人的な動機も、強いコンセプトの原動力になります。
【Who】誰に
次に、誰をターゲットにするかを具体的に設定します。「みんなに愛される店」は理想的に聞こえますが、実際には誰にも刺さらない中途半端な店になりがちです。
年齢、性別、職業、収入、ライフスタイル、価値観など、できるだけ詳細にターゲット像を描きましょう。「30代後半の共働き夫婦、子どもなし、世帯年収800万円、週末は外食を楽しむ」というように、具体的な人物像が浮かぶまで掘り下げます。
さらに、その人たちが抱える課題や欲求も考えます。「平日は忙しくて自炊できない」「健康は気になるが、味も妥協したくない」など、ニーズを深く理解することで、より刺さるコンセプトが生まれます。
【What】何を
ターゲットが明確になったら、その人たちに何を提供するかを決めます。単に「イタリア料理」「ラーメン」という料理ジャンルだけでなく、どんな価値を提供するかまで考えましょう。
「本場の味を再現した本格イタリアン」なのか「日本人の口に合うようアレンジしたイタリアン」なのかで、まったく違う店になります。「素材にこだわった一杯」なのか「コスパ重視のラーメン」なのかも同様です。
料理以外の価値も重要です。「くつろげる空間」「スタッフとの会話」「インスタ映えする見た目」など、トータルで何を提供するのかを明確にしましょう。
【Where】どこで
立地選びは、ターゲット顧客がアクセスしやすく、コンセプトに合った環境であることが重要です。
オフィス街なら平日ランチ需要が見込まれる反面、週末は閑散とします。住宅街なら家族連れが多く、駅前なら会社帰りのサラリーマンが中心になります。それぞれの立地特性を理解し、自店のコンセプトとマッチするかを検証しましょう。
また、1階路面店か2階以上か地下かでも、入りやすさが大きく変わります。隠れ家的なコンセプトなら2階や地下も魅力になりますが、ファミリー向けなら1階路面店が望ましいでしょう。
【When】いつ
営業時間や定休日の設定です。ターゲットのライフスタイルに合わせることが基本ですが、コンセプトとの整合性も大切です。
「朝活をする人のためのカフェ」なら朝7時開店が必要ですし、「仕事帰りに一杯飲める店」なら深夜営業が求められます。「ゆっくり過ごせる週末ブランチの店」なら、平日は休業という選択肢もあります。
定休日も戦略的に設定しましょう。飲食店は火曜定休が多いため、あえて火曜営業にすることで差別化できる場合もあります。
【How】どのように
サービスの提供方法を明確に決めることが重要です。フルサービスにするのか、セミセルフにするのか、あるいは完全セルフサービスにするのかを検討します。また、予約制にするのか、並んで入店できる形にするのかもあらかじめ方向性を定めておきましょう。
たとえば「特別な日のためのレストラン」であれば、完全予約制でフルサービスを導入すると特別感を演出できます。一方で「気軽に立ち寄れる店」であれば、予約不要でセミセルフを取り入れることで利便性を高められます。
また、注文方法(口頭、券売機、タブレット)、会計方法(テーブル会計、レジ会計)、テイクアウトやデリバリーの有無なども、ここで決定します。
【How much】いくらで
価格設定は、提供価値、ターゲットの支払い能力、競合店の価格などを総合的に判断して決めます。
重要なのは「安ければいい」ではないということです。コンセプトに見合った「適正価格」を設定することで、ターゲット顧客に「この価値ならこの価格は妥当」と感じてもらえます。
また、価格設定の際には必ずランニングコストも考慮しましょう。食材費だけでなく、人件費、家賃、光熱費、そして見落としがちな廃棄物処理費用なども含めた上で、持続可能な価格設定をすることが大切です。
コンセプトのアイデア出しにはコンセプトシートを活用しよう
5W2Hで考えた要素を整理し、全体像を俯瞰するためには「コンセプトシート」を活用すると効果的です。コンセプトシートは、各要素を一覧化して相互の関連性や整合性を確認するためのツールとして役立ちます。
コンセプトシートを作成する最大のメリットは、頭のなかにある漠然としたイメージを具体的に「見える化」できることです。紙に書き出すことで矛盾や不足している要素に気づきやすくなります。
さらに、コンセプトシートは事業計画書の作成にも大きな力を発揮します。融資を申請する際には、事業を始める理由や顧客に提供する価値を明確に説明する必要があります。コンセプトシートがあれば、これらの情報を体系的に整理でき、説得力のある事業計画書を仕上げられます。
開業後もコンセプトシートは経営を支える重要なツールです。新メニューの開発や店舗リニューアルの方針を考えるときに立ち返るべき原点となり、新人スタッフの教育にも活用できます。
イーブライトに所属するごみ回収ガールが、インスタグラムでごみに関する情報を配信中!フォローやDMもお待ちしております!
まとめ
飲食店を成功に導くためには、明確で一貫性のあるコンセプトを持つことが欠かせません。5W2Hの思考法を用いれば、想いや情熱を具体的で実現可能なコンセプトへと落とし込むことができます。
ただし、コンセプト設計は理想を描くだけではなく、現実的な経営視点を取り入れることが重要です。とくに見落としやすいのが、日々のランニングコストです。食材費や人件費に加え、廃棄物処理費用を含めた収支計画を立てることで、持続可能な経営を実現できます。
飲食店を運営すると、毎日多くのごみが発生します。生ごみや廃油、ダンボール、ビン・カンなどの処理には想像以上のコストがかかります。
イーブライトでは、廃棄物処理やグリストラップ清掃をはじめ、店舗の衛生環境を守るための多様なサービスを提供しています。また、計量器付きパッカー車を導入しているため、排出量や処分費用を明確に管理できます。
定期回収にも対応しているため、まずはお気軽にお問い合わせください。




