COLUMN コラム
キッチンカー開業のはじめ方!資格や資金・補助金から車の入手方法まで解説

街角やイベントで人気を集めているキッチンカーは、移動できる自由さやイベント・街中での出店機会の豊富さによって、近年さらに注目を浴びています。
しかし、開業には資格取得や営業許可、資金計画など、事前に把握すべき重要なポイントが数多くあります。
本記事では、キッチンカー開業を成功させるために必要な準備に加えて、見落としやすいごみ処理のルールまでを取り上げ、実践的な情報を詳しく解説します。
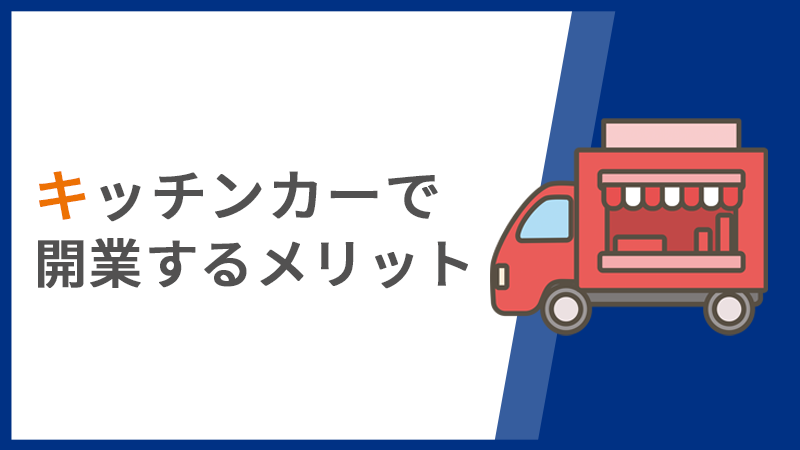
キッチンカーで開業するメリット
キッチンカーは、従来の店舗型飲食店にはない独自の魅力があります。ここでは、キッチンカーで開業するメリットについて見ていきましょう。
開業資金とランニングコストを抑えられる
店舗型飲食店の開業には、一般的に900万〜1,500万円以上の初期費用が必要とされています。物件取得時の敷金・礼金・仲介手数料、内外装工事、厨房設備の購入など、多額の資金が必要になるためです。
一方、キッチンカーの場合、初期費用はおおよそ200万~500万円程度で開業可能です。車両の種類や設備によって変動はありますが、店舗と比較すると大幅にコストを削減できます。
さらに、毎月の家賃という固定費が発生しないため、ランニングコストも抑えやすくなります。必要な経費は、ガソリン代や駐車場代、車両保険料、出店料などに限定されるため、売上に応じて柔軟に経費をコントロールできる点も大きな魅力です。
短期間で開業できる
店舗型飲食店の場合、物件探しから契約、内装工事、設備搬入まで、開業までに半年~1年程度の準備期間が必要です。
一方、キッチンカーの場合、車両の準備と営業許可の取得が完了すれば、最短3か月程度で開業できます。事業計画が固まっている場合、スピーディーに事業をスタートできるため、市場の変化にも素早く対応できます。
好きな時間・場所で営業できる
キッチンカー最大の魅力は、営業場所と時間を自由に選べることです。平日はオフィス街でランチ営業、週末はイベント会場や公園での出店など、曜日や時間帯に応じて最適な場所で営業できます。
天候や季節に応じて出店場所を変更したり、より集客が見込める場所へ移動したりと、固定店舗では不可能な柔軟な対応が可能です。また、自分のライフスタイルに合わせて営業日や営業時間を調整できるため、ワークライフバランスを保ちやすいという利点もあります。
キッチンカーで開業する際の大まかな流れ
キッチンカー開業を成功させるには、計画的な準備が欠かせません。キッチンカーで開業する際の大まかな流れは以下のとおりです。
【ステップ1:事業計画・コンセプトの策定】
まず、どんな料理を、どこで、誰に提供するのかを明確にします。ターゲット層の設定、メニュー構成、価格帯、主な出店場所などを具体的に決めていきます。
【ステップ2:資金計画の作成】
初期費用と運転資金を算出し、自己資金でどこまで賄えるか、融資や補助金をどう活用するかを検討します。売上予測と収支計画も同時に作成します。
【ステップ3:車両の選定・準備】
軽トラック、1tトラック、1.5tトラックなど、メニューや出店場所に適した車両を選びます。新車購入、中古車購入、レンタルなど、予算に応じた調達方法を決定します。
【ステップ4:資格取得・営業許可申請】
食品衛生責任者資格を取得し、出店予定地域の保健所で飲食店営業許可を申請します。地域によって基準が異なるため、早めの確認が重要です。
【ステップ5:設備・備品の準備】
調理器具、食器、容器、のぼり、看板など、営業に必要な設備や備品を揃えます。メニューに応じて必要な機材を選定します。
【ステップ6:出店場所の確保】
イベント会場、オフィス街、商業施設の駐車場など、安定的に出店できる場所を開拓します。複数の出店先を確保することが安定経営のポイントとなります。
【ステップ7:開業・営業開始】
すべての準備が整ったら、いよいよ営業開始です。SNSでの告知や、初回限定サービスなどで集客を図りながら、徐々に認知度を高めていきます。
肝心のキッチンカーはどうやって手に入れる?
キッチンカーの入手方法は大きく分けて4つあります。それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分に最適な方法を選びましょう。
持っている自動車を改造する
すでに所有している車両を改造する方法は、もっとも初期費用を抑えられる選択肢です。改造費用は50万〜150万円程度が相場ですが、車両の状態や改造内容によって変動します。
【メリット】
- 初期費用をもっとも抑えられる方法
- 軽バンやワンボックスカーを活用できる
ただし、すべての車両が改造に適しているわけではないため、事前に専門業者に相談することが重要です。
新車を業者に製作してもらう
キッチンカー専門業者に新車製作を依頼する方法は、理想の仕様を実現できる最良の選択肢です。費用は軽トラックベースで200万〜300万円、1tトラックベースで300万〜600万円が相場です。
【メリット】
- 希望どおりの仕様・デザインを実現できる
- 保健所の基準を満たした安心設計
- 故障リスクが低く、長期的な営業に向いている
ただし、初期投資は大きく、納車までに時間がかかる場合もあるため、注意が必要です。
中古で購入する
中古のキッチンカーを購入する方法は、新車に比べて初期費用を抑えられる選択肢です。価格は100万〜300万円程度が相場で、年式や状態によって幅があります。
【メリット】
- 新車よりも初期費用を抑えられる
- 営業許可対応済みの車両ならすぐに開業できる
ただし、購入前には車両の状態をしっかり確認することが重要です。とくに給排水設備・電気系統・エンジンの状態は念入りにチェックし、修理やメンテナンスが必要な箇所を把握しておきましょう。
レンタルやリースを活用する
初期投資を最小限に抑えたい場合は、レンタルやリースを利用する方法があります。リースは月額5万〜30万円程度が相場です。
【メリット】
- 初期費用を大幅に抑えられる
- レンタルなら短期間・試験出店に最適
- リースなら自分の車を持たずに中長期の営業が可能
ただし、長期的に見ると購入より総額が高くなる場合があるため、注意が必要です。
キッチンカーの開業に必要な資金と資金調達方法
キッチンカー開業には、車両費用だけでなく、さまざまな初期費用と運転資金が必要です。具体的な費用の内訳と、資金調達の方法について詳しく解説します。
キッチンカーの開業に必要な資金
開業に必要な資金は、大きく分けて初期費用と運転資金の2つに分類されます。
キッチンカーの費用
車両本体と改装費用が、初期投資の大部分を占めます。
軽トラックベースの場合、新車で200万〜300万円、中古で100万〜200万円程度が目安です。1tトラックベースなら、新車で300万〜600万円、中古で150万〜500万円程度となります。
レンタルを選択する場合は、初期費用は大幅に抑えられますが、月々のレンタル料が発生することを考慮する必要があります。
設備・消耗品費
調理器具に7万~20万円、設備などの内装に50万~150万円ほどの費用がかかります。
フライヤー、鉄板、冷蔵庫、冷凍庫などの調理機器に加え、調理器具、食器、カトラリーなどの備品も必要です。さらに、のぼり、看板、タペストリーなどの販促物、初回仕入れ分の食材費用も準備しておく必要があります。
営業許可申請費用や食品衛生責任者講習費用、各種保険料なども含めると、車両以外に60万〜150万円程度は見込んでおくべきでしょう。
キッチンカーの運転資金も考慮しておこう
開業後すぐに黒字化することは難しいため、3か月〜6か月分の運転資金を準備しておくことが重要です。
毎月の経費として、ガソリン代が2万〜5万円、駐車場代が2万〜6万円、出店料が3万〜10万円、食材仕入れ費が売上の30%程度、その他消耗品費などが必要になります。
さらに、生活費も含めて考えると、月額30万〜50万円程度の運転資金を確保しておくと安心です。
季節による売上変動や天候不良による営業中止なども想定し、余裕を持った資金計画を立てることが大切です。
キッチンカーの開業資金を調達する方法
必要な資金をすべて自己資金で賄うのは難しい場合が多いため、さまざまな資金調達方法を検討しましょう。
自己資金を使う
もっともリスクが低い方法は、自己資金での開業です。借入金がないため、返済の心配がなく、経営の自由度も高くなります。
ただし、すべてを自己資金で賄おうとすると、開業後の運転資金が不足する可能性があります。自己資金は全体の3分の1〜半分程度に留め、残りはほかの方法で調達するバランスが理想的です。
金融機関や日本政策金融公庫から融資を受ける
銀行や信用金庫からの融資は、一般的な資金調達方法です。ただし、実績のない新規開業の場合、審査が厳しくなる傾向があります。
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金制度なら、無担保・無保証で最大7,200万円まで融資を受けられる可能性があります。金利も比較的低く、創業計画書がしっかりしていれば、実績がなくても融資を受けやすいという特徴があります。
融資を受ける際は、詳細な事業計画書と収支計画書の作成が必須です。売上予測の根拠や返済計画を明確に示すことで、融資の可能性が高まります。
出典:日本政策金融公庫(https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html)
補助金を活用する
返済不要の補助金は、開業資金の負担を大きく軽減できる魅力的な選択肢です。ただし、補助金は後払いが基本であり、採択されるまでに時間がかかることも考慮する必要があります。
キッチンカーの開業に活用できる主な補助金
キッチンカー開業の資金負担を軽減できる補助金制度について、それぞれの特徴と活用方法を解説します。
なお、補助金の要件は公募次第によって変更される場合があるため、必ず最新の公募要領を確認してください。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業の生産性向上を支援する制度です。補助額は100万〜1,500万円で、補助率は通常枠の2分の1となっています。
キッチンカー事業では、主に厨房機器や改装費用が補助対象となります。車両本体の購入費は原則として対象外ですが、既存車両の改装費用や、調理効率を向上させる設備投資は対象となる可能性があります。
申請には、革新的なサービス開発や生産プロセスの改善など、付加価値向上の取り組みを明確に示す必要があります。
出典:ものづくり補助金ウェブサイト(https://portal.monodukuri-hojo.jp/)
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化を支援する制度です。補助額は通常枠で50万円、インボイスや賃上げといった特定の条件を満たすことで最大250万円まで、補助率は3分の2です。
キッチンカー事業では、看板やのぼりなどの販促物製作、ホームページ制作、チラシ作成などの広告宣伝費が補助対象となります。車両ラッピングや、新メニュー開発のための試作費用も対象になる場合があります。
申請のハードルが比較的低く、採択率も高いため、初めて補助金を申請する方にもおすすめです。商工会議所や商工会の支援を受けながら申請書を作成できる点も大きなメリットです。
出典:中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/jizoku/)
中小企業新事業進出促進事業
中小企業新事業進出促進事業は、新分野展開や業態転換を支援する制度です。これは事業再構築補助金の後継制度として位置づけられており、補助額は750万〜9,000万円と幅広く設定されています。
既存の飲食店がキッチンカー事業に進出する場合や、異業種からの新規参入の場合に活用できる可能性があります。ただし、売上高減少要件など、申請要件が細かく設定されているため、事前の確認が必須です。
補助対象経費は幅広く、建物費、機械装置費、広告宣伝費などが含まれます。ただし、車両本体が対象となるかは公募要領で確認が必要です。
出典:中小企業基盤整備機構ウェブサイト(https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/)
キッチンカーの開業に必要な手続き・資格
キッチンカーで合法的に営業するためには、必要な資格の取得と営業許可の申請が欠かせません。2021年6月の食品衛生法改正により、手続きが一部変更されているため、最新の情報にもとづいて準備を進めましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は、キッチンカー営業に必須の資格です。各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会を受講することで取得できます。
講習は1日(約6時間)で完了し、食品衛生学、食品衛生法、公衆衛生学などを学びます。受講料は1万〜12,000円程度で、2025年4月以降は全国的に値上げされる予定です。
なお、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている場合は、講習が免除されます。これらの資格をお持ちの方は、そのまま食品衛生責任者として登録できます。
出典:一般社団法人東京都食品衛生協会ウェブサイト(https://www.toshoku.or.jp/training/)
飲食店営業許可
2021年6月の食品衛生法改正により、キッチンカーの営業許可は「飲食店営業」に一本化されました。以前は「菓子製造業」「喫茶店営業」など、メニューによって異なる許可が必要でしたが、現在は調理を伴うすべての営業が「飲食店営業」として統一されています。
営業許可を取得するには、出店予定地域を管轄する保健所に申請します。申請には、営業許可申請書、車両の平面図、食品衛生責任者の資格証明書などが必要です。申請手数料は16,000〜2万円程度が一般的です。
保健所の職員による車両検査では、給排水設備、手洗い設備、冷蔵・冷凍設備などが基準を満たしているかチェックされます。とくに給排水タンクの容量は重要で、40L、80L、200Lの3段階で提供できるメニューの範囲が変わります。
40Lタンクでは単品メニューのみ、80Lタンクでは2工程程度の簡単な調理まで、200Lタンクでは本格的な調理や仕込みも可能になります。
仕込み場所の確保も営業許可の重要なポイントです。自宅での仕込みが認められない地域も多く、その場合は飲食店営業許可を持つ施設を借りる必要があります。シェアキッチンやレンタルキッチンを活用する方法もあり、使う頻度によりますが月額2万〜5万円程度で利用できる施設も増えています。
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html)
車内で調理しない場合は「営業届出」が必要
包装済みの食品のみを販売する場合や、温めるだけの簡易な調理のみを行う場合は、営業許可ではなく「営業届出」で済む場合があります。
営業届出は許可よりも手続きが簡単で、手数料も不要です。ただし、提供できる商品が限定されるため、事前に保健所で確認することが重要です。
【注意】出店する地域ごとに営業許可を取ろう!
キッチンカーの営業許可は、出店する地域ごとに取得する必要があります。東京都で許可を取得しても、神奈川県や千葉県で営業する場合は、それぞれの地域で別途許可が必要です。
都道府県によっては、県内全域で有効な許可もあれば、市町村単位での許可が必要な場合もあります。複数の地域で営業を予定している場合は、各地域の保健所に事前に確認し、必要な許可をすべて取得しておきましょう。
また、地域によって車両の基準や必要書類が異なる場合があるため、それぞれの要件を満たす準備が必要です。許可取得には時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで申請することが大切です。
キッチンカー開業でありがちな失敗と対策ポイント
キッチンカー開業後に直面しやすい課題と、それらを回避するための具体的な対策について解説します。事前にリスクを把握し、対策を講じることで、安定した経営を実現できます。
出店場所が悪い・確保できない
キッチンカー経営でもっとも多い失敗が、出店場所の問題です。人通りの少ない場所では売上が伸びず、よい場所が確保できなければ営業自体ができません。
対策として、開業前から複数の出店候補地をリストアップし、実際に足を運んで人の流れや競合店の状況を調査しましょう。平日と週末、時間帯による違いも把握することが重要です。
出店場所の開拓には、イベント主催者への直接営業、キッチンカー専門の仲介サービスの活用、SNSでの情報収集などが効果的です。また、ほかのキッチンカー事業者とのネットワークを構築し、情報交換することも有効な手段です。
価格設定を間違えて収益が出ない
原価計算が甘く、利益が残らない価格設定をしてしまうケースも少なくありません。食材費だけでなく、ガソリン代、出店料、人件費などすべてのコストを考慮する必要があります。
まず、原価率は30%以下を目標に設定しましょう。1食あたりの食材費、容器代、調味料費などを正確に計算し、そこに経費と利益を上乗せして販売価格を決定します。
競合他社の価格調査も重要ですが、安易な値下げ競争は避けるべきです。むしろ、ボリュームや品質、サービスで差別化を図り、適正な価格で勝負することが長期的な成功につながります。
集客が思うようにできない
せっかくよい商品を作っても、知ってもらえなければ売上にはつながりません。とくに開業直後は認知度が低く、集客に苦戦することが多いです。
SNSを活用した情報発信は必須です。Instagram、X(旧Twitter)、Facebookなどで、日々の出店情報、メニュー写真、メニューの評判などを積極的に投稿しましょう。
具体的なSNS活用のコツとして、Instagramでは料理の調理過程を動画で見せる、出店場所の風景とセットで撮影する、顧客の笑顔を撮影する(許可を得て)などが効果的です。投稿時間は、ランチ前の11時頃や夕食前の17時頃がエンゲージメント率が高くなる傾向があります。
また、初回限定割引、スタンプカード、SNSフォロー特典など、リピーター獲得のための仕組みづくりも重要です。美味しい料理だけでなく、親しみやすい接客でファンを増やしていくことが、安定経営へのポイントです。
悪天候などの影響で売上が伸びない
雨や強風、猛暑や極寒など、天候はキッチンカーの売上に大きく影響します。
まず、年間の収支計画を立てる際は、悪天候による営業中止日を想定に入れておくことが重要です。月間営業日数の20%程度は天候不良を見込んでおくと安全です。
対策として、屋根のある場所や屋内イベントへの出店を増やす、テイクアウト需要の高いメニューを開発する、UberEatsなどのデリバリーサービスを併用するなどの方法があります。
また、天候に左右されにくい企業向けのケータリングサービスを展開するのもひとつの選択肢です。
開業前にチェック!キッチンカーのごみ処分ルール
キッチンカー営業では、意外と見落とされがちなのがごみの適切な処分方法です。事業活動で出るごみは「事業系ごみ」に分類され、家庭ごみとは異なる処理が必要です。
【ごみの分類】
- 事業系一般廃棄物:生ごみ、野菜くず、食べ残し、紙ナプキン、割り箸など
- 産業廃棄物:プラスチック容器、ビニール袋、発泡スチロール容器、廃油、アルミホイルなど
これらを家庭ごみとして出すことは不法投棄にあたり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。出店場所のごみ箱に勝手に捨てることも、契約違反や信用失墜につながるため絶対に避けるべきです。
ごみ処理の基本的な方法は、許可を得た廃棄物処理業者に収集を依頼することです。一般廃棄物は「一般廃棄物収集運搬業許可」を持つ業者に、産業廃棄物は「産業廃棄物収集運搬業許可」を持つ業者に、それぞれ委託する必要があります。
イーブライトに所属するごみ回収ガールが、インスタグラムでごみに関する情報を配信中!フォローやDMもお待ちしております!
まとめ
キッチンカー開業は、店舗型飲食店と比べて初期費用を抑えながら、自由度の高い営業ができる魅力的な事業です。成功のためには、資金計画の精査、出店場所の確保、効果的な集客施策など、入念な準備と継続的な努力が欠かせません。
とくに、事業系ごみの適切な処理は、見落とされがちですが、継続的な営業に不可欠な要素です。廃棄物処理法に違反すると、罰則だけでなく営業停止のリスクもあります。開業準備の段階で、信頼できる廃棄物処理業者と契約しておくことが、安定経営の基盤となります。
イーブライトでは、ごみ処理をトータルでサポートしています。一般廃棄物から産業廃棄物まで一括で対応でき、出店スケジュールに合わせて柔軟な回収プランを提供しています。開業準備でお悩みの方、ごみ処理について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。




