COLUMN コラム
産業廃棄物のマニフェストが不要なケースとは?注意点を解説

産業廃棄物を処理業者に委託する際には、廃棄物の種類ごとにマニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成する必要があります。そのため、大量の廃棄物を排出する企業では、管理が煩雑になり、事務作業の負担が大きくなることもあります。
しかし、すべてのケースでマニフェストの交付が義務付けられているわけではありません。法律で特別に定められた条件を満たす場合に限り、マニフェストの交付が不要となることがあります。
本記事では、産業廃棄物に関するマニフェストの交付が不要となる10のケースについて詳しく解説します。マニフェストが不要な場合に注意すべき点についても取り上げていますので「事務作業の負担を軽減したい」「法的リスクを未然に防ぎたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
産業廃棄物の処理でマニフェストが不要なケース
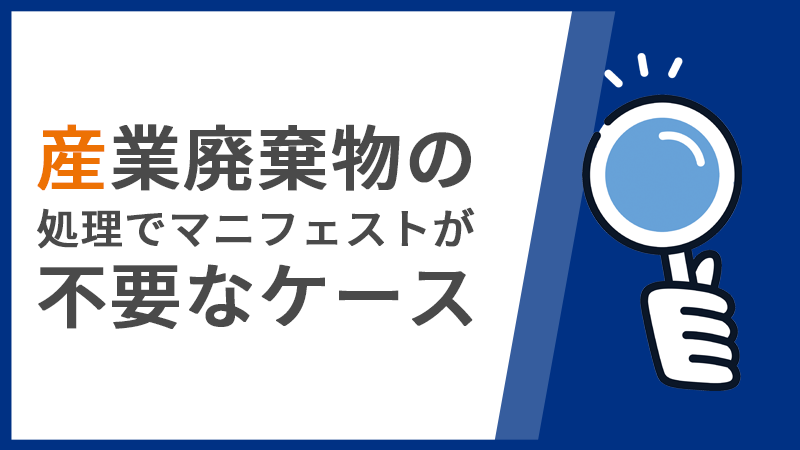
マニフェストは、産業廃棄物が適正に処理されたかを確認するための管理票です。廃棄物を出す会社(排出事業者)は、廃棄物の種類や量、運搬業者・処理業者の情報を記入し、廃棄物と一緒に業者へ渡します。
このマニフェストによって、廃棄物がどのように処理されたのかを追跡でき、不適切な処理や不法投棄を防げます。マニフェストの交付は法律で義務づけられており、作成しないまたは虚偽の記載をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されるおそれがあります。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十七条の二(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
ただし、法令でマニフェストの交付が不要とされている場合には、作成しなくても法的な罰則は発生しません。以下では、マニフェストが不要となるケースについて紹介します。
国に委託する場合
産業廃棄物の処理を国に委託する場合、マニフェストの作成は必要ありません。国の管理のもとで適正に処理されることから、不適切な処理が行われるリスクが少ないため、マニフェストによる追跡を行わなくても問題ないとされています。
都道府県・市区町村に委託する場合
産業廃棄物の処理を都道府県や市区町村に委託する場合、マニフェストは必要ありません。
自治体が責任を持って適正に処理を行うため、不法投棄や不適切な処理のリスクが低いためです。
ただし、すべての自治体が産業廃棄物を受け入れているわけではないため、事前に対応可能かどうか確認しておきましょう。
都道府県知事の指示を受けた業者に委託する場合
産業廃棄物の処理を都道府県知事の指示を受けた業者に委託する場合、マニフェストの作成義務はありません。指示を受けた業者は、すでに都道府県知事の認可を受けているとみなされるためです。
専ら業者に委託する場合
専ら(もっぱら)業者に委託する場合は、マニフェストを作成する必要がありません。専ら業者とは、特定の廃棄物をリサイクル目的で扱う専門業者のことです。
一般的な廃棄物処理業者とは異なり、専ら物(もっぱらぶつ)を扱う場合、処分業の許可が不要です。廃棄物処理業者に定められた処理ルールが適用されないため、交付義務がありません。
ただし、専ら物として扱われるのは、ほぼ100%リサイクル可能なものに限られます。代表的な品目は以下の4つです。
・古紙(新聞紙・ダンボールなど)
・くず鉄(鉄スクラップなど)
・空きビン類(ガラスくず)
・古繊維(古着・布製品)
また、専ら業者は「廃棄物」を扱う処分業者のため、有価物を扱っている場合は、専ら業者とは認められません。たとえば以下の業者のことです。
・古紙をトイレットペーパーと交換する業者
・金属スクラップを買い取る業者
さらに、古紙やくず鉄などなら、必ず専ら物になるわけでもありません。次のような場合は専ら物と認められない場合があり、通常の交付義務があります。
アスベストやPCBなどの有害物質が含まれている場合
ほかの廃棄物が混ざっている場合
専ら業者に委託する際は、廃棄物の状態を事前に確認することが重要です。
再生利用認定制度の認定を受けた業者に委託する場合
産業廃棄物の処理を再生利用認定制度の認定を受けた業者に任せる場合、マニフェストの交付義務はありません。再生利用認定制度とは、環境省が定めた廃棄物を、適切・安全にリサイクルできる業者に与えられる認定制度です。
この制度によって、認定を受けた業者は、特定の廃棄物を処理する際に、廃棄物処理業の許可や処理施設の設置許可、マニフェストの発行が不要になります。
対象になるのは、以下の廃棄物です。環境省は、再生利用が可能で、安全に処理できる廃棄物を個別に定めています。
【一般廃棄物、産業廃棄物】
1.廃タイヤ(自動車用に限る)に含まれる鉄を、セメントをつくるときの原料として使う場合
2.廃タイヤなどのゴム製品を製鉄所の設備で鉄に戻し、その鉄を鉄鋼製品の原料として使う場合
3.廃プラスチックを鉄づくりに使う高炉の燃料(還元剤)として再利用する場合(次の4番に該当するものを除く
)
4.廃プラスチックをコークス炉で処理し、コークスや炭化水素油に変えて再利用する場合
5.処理場から出た廃肉骨粉に含まれるカルシウムを、セメントの原料として使う場合
6.適切に除湿処理をした廃木材を、製鉄所の設備で鉄に戻し、その鉄を鉄鋼製品の原料として使う場合(構造改革特別区域に限る)
7.金属を多く含む廃棄物から、鉱物の処理工程で出る副産物などを原料として使い、非鉄金属や鉄をつくる工場で金属を再生する場合
【産業廃棄物のみ】
8.特定の工事で発生した無機性の建設汚泥を、河川管理者の仕様に従って高規格堤防の建設に使うため再利用する場合
9.半導体や太陽電池などの製造工程で出たシリコンを含む汚泥を脱水し、加工して、製鉄用の溶鋼の脱酸に使う場合
ただし、以下のような廃棄物は、環境や健康への悪影響が懸念されるため、この制度の対象外となります。
・ばいじんや焼却灰
・鉛蓄電池やシュレッダーダスト
・食品残渣や下水汚泥
産業廃棄物の種類や再利用の目的によっては、交付が必要になる場合があります。環境省の「再生利用認定制度の手引き」を確認し、適切に対応しましょう。
出典:環境省 再生利用認定制度申請の手引き(https://www.env.go.jp/content/900536147.pdf)
広域的処理認定制度の認定を受けた業者に委託する場合
広域認定制度(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)は、製品を作った企業が、その製品が不要になった後の処理にも関わることで、効率的なリサイクルや適切な処理を進めることを目的とした制度です。
たとえば、パソコンや消火器などは、通常の廃棄物と同じ方法で処理すると環境に悪影響を与える可能性がありますが、メーカーが責任を持って回収・処理できる仕組みを作ることで、安全かつ適切な処理を実現しています。この制度により、メーカーが処理に関与することで、リサイクルしやすい製品の設計が進み、環境負荷の低減が期待されます。
また、環境省の認定を受けた業者は、特別な許可を取得せずに全国規模で製品を回収・処理できるのも特徴です。通常、産業廃棄物は自治体ごとの許可が必要ですが、広域認定制度を利用すれば、都道府県をまたいで回収することが可能です。
ただし、利用する際は、以下の3つの条件を満たす必要があります。
・環境大臣の認定を受けた業者が処理を行うこと
・環境大臣から「広域的処理認定業者」として正式に認められた業者であることが条件です。
・製造メーカーが自社製品を回収・処理すること
メーカー自身が、自社の製品を回収して適切に処理する場合に限られます。たとえば、パソコンメーカーが、使い終わった自社製パソコンを回収してリサイクルするケースが該当します。
・廃棄物が広域的処理認定制度の対象品目であること
リサイクルを目的とした使用済み製品などの特定の廃棄物が対象となります。使用済みパソコン、消火器、建材などがこの制度の対象に含まれます。
広域認定制度では、自社製品をメーカーが直接回収・処理できるため、不法投棄のリスクを減らせます。しかし、すべての産業廃棄物が対象になるわけではなく、次のようなものは対象外となります。
・腐りやすいものや変化しやすいもの
運ぶ途中で腐る、または臭いが出るものは、この制度では処理できません。
・ほかの製品と見分けがつかないもの
発泡スチロールやPPバンド(荷物を縛るプラスチックのひも)などは、どの会社の製品かわかりにくいため、広域認定制度の対象になりません。
出典:環境省 広域認定制度申請の手引き (https://www.env.go.jp/content/000287511.pdf)
運搬用パイプラインなどの処理施設を用いる業者に委託する場合
運搬用のパイプラインなどを利用した処理設備を使用する業者に委託する場合、マニフェストの発行義務はありません。
運搬用パイプラインは、廃棄物をそのまま処理施設に直結させて運ぶ設備です。廃棄物を途中でほかの場所に流出させることがないため、産業廃棄物の追跡が不要となります。
産業廃棄物を輸出する運搬業者に委託する場合
産業廃棄物を海外に輸出する際、輸出専門の運搬業者に依頼すれば、マニフェスト作成義務はありません。マニフェストは、国内で産業廃棄物が適正に処理されることを確認するための制度だからです。
海外に輸出された廃棄物は、日本国内で処理されないため、マニフェストの対象外になります。輸出専門の運搬業者に委託した場合は、交付義務はありません。
廃油の処理を行う湾岸管理者・漁港管理者に委託する場合
廃油を処理する際、湾岸管理者や漁港管理者に依頼すると、マニフェスト作成義務はありません。湾岸管理者や漁港管理者は、国土交通大臣から廃油の運搬・処分に関する許可を受けているため、特別にマニフェストが免除されているためです。
廃油の処理を行う海洋汚染防止法の規定許可を受けている業者に委託する場合
海洋汚染防止法にもとづく許可を受けた業者に委託すれば、マニフェストの発行義務はありません。海洋汚染防止法とは、正式名称は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」で、船から油や有害物質、廃棄物が海に流れるのを防ぐためのものです。
イーブライトでは、廃棄物処理法を遵守し、
お客様のニーズに合わせたゴミ回収サービスを提供しています。
ぜひご覧ください。
産業廃棄物委託契約書を忘れずに作成しよう!
産業廃棄物の処理を業者に委託する際、マニフェストの交付が不要な場合でも「産業廃棄物処理委託契約書」の作成が必要です。産業廃棄物処理委託契約書は、委託内容を明確にし、適正な処理を確保するための重要な書類となります。
もし契約を結ばずに委託すると、法律違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。適正な処理のためにも、必ず契約を結びましょう。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137/#Mp-Ch_5-At_28)
また、契約書・マニフェスト・業者の許可証や認定証は、契約終了後も5年間の保管が義務付けられています。紛失しないよう適切に管理することが大切です。
マニフェストは廃棄物の種類ごとに作成が必要なため、大量の廃棄物を排出する事業者にとっては管理が煩雑になりがちです。事務作業の負担を減らしたい場合は、電子マニフェストの導入を検討しましょう。
電子マニフェストは、インターネット上でマニフェストを管理できるシステムです。保存する手間や物理スペースを省略でき、行政への実績報告も不要です。処理状況をすぐに確認できるので事務作業の負担軽減につながります。
マニフェストの管理が大変な場合は、電子マニフェストの導入を検討するとよいでしょう。
まとめ
産業廃棄物を処理業者に委託する場合は、原則としてマニフェストの交付が義務付けられています。しかし、国・自治体に委託する場合や都道府県知事の指示を受けた業者に委託する場合は、必要ありません。国や自治体の責任で廃棄物が処理されるためです。
また、専ら業者や再生利用認定制度・広域的処理認定制度の認定を受けた業者に委託する場合もマニフェストはいりません。リサイクル目的であり、一部は環境省の認定を受けているためです。ほかにも、運搬用のパイプラインなどを利用した処理設備を使用する業者や産業廃棄物を輸出する運搬業者などもマニフェスト交付義務はありません。
ただし、マニフェストが不要な場合であっても、廃棄物処理委託契約書の作成は義務づけられています。これを怠ると罰則を受ける可能性があるため、注意しましょう。マニフェストの発行が必要な場合でも、電子マニフェストを活用すれば、紙の手続きの手間を大幅に削減できます。
株式会社イーブライトは、横浜市・川崎市を中心に事業系ごみの回収サービスを提供している企業です。イーブライトなら電子契約や電子マニフェストに対応しているため、業務効率の向上・コスト削減・スピーディーな契約が可能です。




