COLUMN コラム
飲食店の廃業率は業種別で最多!その原因と生き残るためのポイントを解説

飲食店は、開業のハードルが比較的低い一方で、廃業率が高い業種のひとつといわれています。実際のところ、開業から数年以内に閉店へ追い込まれるケースも多く「味やサービスに自信があっても長く続けられない」という現実があります。
飲食店が廃業に陥りやすいのは、利益構造の厳しさや人手不足、集客の難しさなど、複数の要因が重なっているためです。
本記事では、飲食店の廃業率に関する最新データと、長く愛される店を作るための実践的なポイントを解説します。
飲食店の廃業率は5.6%と業種別最多
飲食業界は、ほかの業種と比べても「開業しやすく、廃業しやすい」構造を持つ業界です。
中小企業庁の調査によれば、宿泊業・飲食サービス業の廃業率は5.6%で、全業種のなかで最も高い水準にあります。 一方で、開業率も17.0%と非常に高く、他業種と比べても新規参入が活発です。
出典:帝国データバンク「https://www.tdb.co.jp/report/industry/20250114-insyokutousan/」
出典:中小企業庁「https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/shokibo/b1_1_2.html」
業態別の廃業件数
帝国データバンクの調査によると、2024年の飲食店倒産件数は894件で過去最多を記録しました。業態別に見ると「酒場・ビヤホール」が212件で最多、次いで「中華料理店」158件「西洋料理店」123件「日本料理店」77件と続きます。
とくに居酒屋業態は、コロナ禍以降のアルコール離れや在宅勤務の定着によって利用頻度が減少しました。加えて、原材料費や人件費、光熱費の上昇が経営を圧迫しています。ラーメン店やカフェも競合が多く、価格競争や差別化の難しさが経営リスクを高める要因になっています。
倒産した店舗の約9割は小規模事業者であり、個人経営や家族経営の店舗が経費上昇に耐えきれず閉店に至るケースが多いのが現状です。
廃業した飲食店の営業年数
飲食店の廃業時期には明確な傾向があります。 開業から1年以内に約3割が閉店、2年以内で約5割、3年以内には6〜7割が廃業しているというデータが出ています。これはつまり、開業から3年を乗り越えられるかどうかが生存の分かれ道であることを示しています。
飲食店ドットコムの調査では、とくに「ラーメン」「カフェ」「そば・うどん」などは6割以上が3年以内に閉店しています。これらの業態は開業しやすい反面、競合が多く、トレンドや立地の影響を受けやすいことから、短期間で売上が変動しやすい傾向があります。
一方「寿司店」や「和食店」は職人技や顧客との信頼関係が重視される業態であり、参入のハードルが高い分、経営が比較的安定しやすい傾向があります。
長く続いている店舗では、味やサービスの質の高さに加えて、地域とのつながりや常連客の維持といった地元密着型の経営が成功要因となっています。
出典:飲食店ドットコム「https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000649.000001049.html」
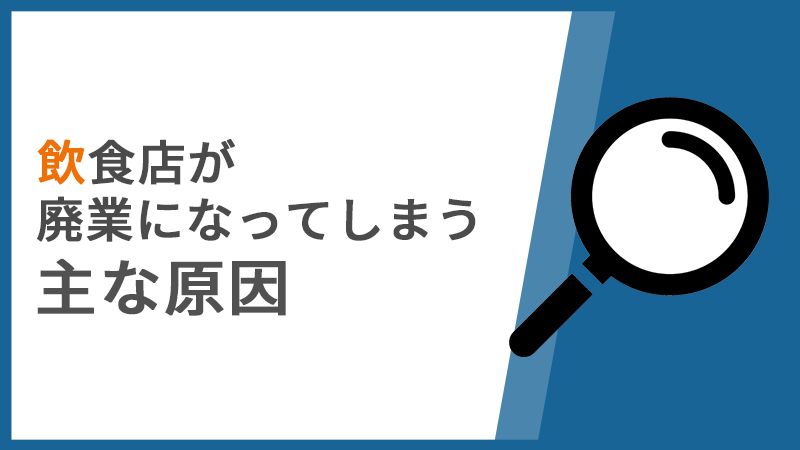
飲食店が廃業になってしまう主な原因
飲食店が廃業に追い込まれる理由は複数の問題が絡み合っています。ここでは、代表的な要因を見ていきましょう。
そもそも利益を出すのが難しい業界であること
飲食業界は、ほかの業種に比べて利益率が低く、経営が安定しにくい構造的な課題を抱えています。 原材料費や人件費、光熱費などの固定費が高い一方で、販売価格を自由に上げにくいという特徴があります。
さらに、仕入れ価格の変動や人手不足、天候や景気に左右されやすい点も経営を難しくしている要因です。また、競合が非常に多く、立地や評判、メニューの人気などによって売上が大きく変動します。
新規出店時には初期投資がかさむため、開業後しばらくは赤字が続くケースも少なくありません。
景気や社会情勢の影響を受けやすい業界であること
飲食業界は、景気の変動や社会情勢の影響を受けやすい典型的な業種です。 2020年には新型コロナウイルスの感染拡大により来店客が激減し、倒産件数が780件に達して過去最多を更新しました。
その後、各種支援策や給付金により2022年は452件まで抑えられたものの、2023年以降は支援終了とともに融資返済が本格化し、再び倒産が増加傾向にあります。
また、近年は物価高騰・光熱費上昇・人手不足といった要因が経営を圧迫しており、景気の後退や感染症流行、災害などの外的要因が直撃しやすい業界構造といえます。
こうしたリスクに備えるには、テイクアウト・デリバリー・オンライン販売などの多チャネル化が欠かせません。加えて、仕入れルートの分散やキャッシュフロー管理の徹底、非常時のオペレーション体制を整えておくことも、持続的な店舗運営に欠かせないポイントです。
初期費用が多くかかり回収に時間がかかること
飲食店の開業には、多額の初期投資が必要です。
一般的に、個人で10〜15坪ほどの店舗を新規で立ち上げる場合、内装工事・厨房設備・什器・初期在庫・広告費などを含めると約1,000万円前後かかるといわれています。物件を一からつくるスケルトン物件であれば、それ以上の費用がかかることも珍しくありません。
一方で、飲食店の平均利益率は10%前後にとどまり、投資を回収するまでには数年を要します。開業当初は売上が安定せず、宣伝や人件費などの支出が先行するため、キャッシュフローの悪化で廃業に追い込まれるケースも少なくありません。
一度はじめるとやり直しが効きにくいこと
飲食店は開業後の方向転換が難しくなります。たとえ立地の課題に気づいても、内装工事や厨房設備に多額の投資をしているため、容易に移転できません。
だからこそ、開業前の徹底したリサーチと事業計画が重要です。昼夜の人通り、周辺住民の属性、競合の位置関係などのデータを幅広く集め、総合的に判断してください。
運転資金が底をつくケース
飲食店が廃業に至る最も多い理由は、運転資金の不足による資金ショートです。多くの個人経営者が、開業資金のほとんどを店舗の初期投資に充ててしまい、日々の支払いに必要な運転資金を確保できないままスタートしてしまいます。
実際、開業直後から黒字化できる店舗はごくわずかです。一般的には半年から1年ほど赤字が続くことを前提に、余裕を持った資金計画を立てる必要があります。
売上が伸び悩んでも、家賃・人件費・仕入れ・光熱費といった固定費は毎月発生し続けるため、資金繰りが苦しくなると一気に経営が行き詰まってしまいます。
人手不足で店が回らないケース
飲食業界では、人材確保の難しさが年々深刻化しています。長時間労働や不規則なシフトが敬遠されやすく、加えて少子高齢化の影響もあり、求人を出しても応募が集まりにくい状況が続いています。
人手が足りないと、接客や調理の品質低下、営業時間の短縮、オーナー自身の長時間労働といった悪循環に陥りがちです。さらに、採用を優先して賃金を上げれば人件費が膨らみ、経営を圧迫する要因にもなります。
経営のスキルや計画が不足していたケース
料理の技術と経営のスキルはまったくの別物です。飲食店経営には、資金計画・在庫管理・原価計算・マーケティングなど、幅広い知識と判断力が求められます。
経営ノウハウが不足していると、原価率を把握しないまま価格を設定して赤字を招くなど、致命的なミスにつながりかねません。
こだわりを持ちすぎてニーズとのズレが生じたケース
オーナーの強いこだわりが、かえって顧客のニーズとずれてしまうケースも少なくありません。オーナー自身の好みや理想と、地域の利用客が求める味や雰囲気は必ずしも一致しないものです。
成功している飲食店は「こだわり」と「顧客ニーズ」のバランスをうまく取っています。開業後も、顧客アンケートの実施や口コミサイトのレビュー確認などを通じて、常にお客様の声に耳を傾け、柔軟に方向修正していく姿勢が大切です。
経営者の年齢層が高いケース
飲食店業界では、経営者の高齢化が深刻な課題となっています。厚生労働省の調査によると、飲食店経営者のうち60歳以上が約55%を占めており、他業種と比べても高い水準です。
長年にわたり地域で親しまれてきた名店であっても、体力的な限界や健康上の理由から経営を続けることが難しくなるケースが増えています。
さらに、後継者不足も大きな問題です。個人経営の飲食店で「後継者がいる」と答えた割合はわずか28.4%にとどまり、多くの店舗が事業承継のめどが立たないまま廃業を選択しています。
結果として、経営は安定しており黒字であっても閉店する「黒字廃業」が年々増加しているのが現状です。
出典:厚生労働省ウェブサイト「https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001041526.pdf」
自分の飲食店が廃業になる可能性を抑えるためのポイント
廃業リスクを完全にゼロにすることは難しくても、経営の工夫次第で大きく抑えることは可能です。ここでは、経営を安定させ、長く愛されるお店を続けていくために意識したいポイントを紹介します。
資金計画と収支管理を徹底する
資金計画と収支管理を徹底することは、飲食店経営を安定させるうえで最も重要なポイントです。
まず、損益分岐点(必要売上=固定費 ÷ 粗利率)を算出し、毎週の売上・原価・人件費の動きを追えるようにしましょう。FLコスト(食材+人件費)は原則合計で60%以内、家賃は売上の10〜15%以内が目安です。
どれかが基準を超えた場合は、メニュー内容の見直しや仕込みの効率化、回転率アップなど、早急な改善を行うことが重要です。
また、会計ソフトと在庫管理システムを連携させ、仕入・売上・在庫をリアルタイムで可視化できる仕組みを導入すると、無駄の削減に役立ちます。
さらに、運転資金は最低2〜3か月分を確保し、売上減少や設備トラブルなど突発的な出費に備えることが大切です。補助金や助成金も積極的に活用し、公募スケジュールを年間で管理することで、安定した資金繰りを実現できます。
こちらの記事では、飲食店の利益率は平均について解説しています。計算方法や利益率アップのポイントも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
集客できる立地を選ぶ
まずは、ターゲット層の行動パターン(平日・休日、昼・夜)を実際に現地で観察し、時間帯ごとの通行量や視認性、競合店の価格帯・席数などを数値で整理しましょう。
立地の良し悪しは、駅からの距離だけで決まりません。交差点や通りからの見えやすさ、看板設置の可否、デリバリー対応エリア、駐車のしやすさといった要素も集客力を左右します。
家賃は「現実的な売上予測 × 粗利率 × 安全係数0.8」で支払可能額を確認し、内装投資についても「投資額÷月間営業利益=回収までの月数」として、明確な回収計画を立てることが重要です。
マーケティングや販促を継続的に行う
デジタル販促は「一度やって終わり」ではなく、継続することが成果につながります。Googleビジネスプロフィールでは、カテゴリの最適化・写真の定期更新・混雑時間の登録・投稿機能の活用をルーティン化しましょう。
SNSでは「料理」「人」「裏側(仕込みやストーリー)」の3つの切り口で発信するのが効果的です。週3回の投稿と、月に数本のショート動画更新を目安に続けることで、ファンの定着を狙えます。
グルメサイトは最低限の露出を維持しつつ、定期的に費用対効果を見直します。LINE公式アカウントでは「初回来店特典」と「3回目来店で使える再来店特典」を組み合わせると、リピート率向上に効果的です。
QSCの向上に絶えず取り組む
品質(味・盛り付け・提供スピード)、サービス(挨拶・気配り・提案力)、清潔(客席・トイレ・入口まわり)を軸にチェックリストを作成し、開店前と閉店前の各5分で必ず確認しましょう。
看板メニューの提供時間は「注文から10分以内」をKPIとして設定します。トイレは1日数回、写真付きで清掃状況を記録し、日報に添付します。さらに、月1回のロールプレイ研修やミニテストを行い、接客や品質基準をスタッフ全員で共有します。
個人の経験や感覚に頼らない標準化されたサービス運営を徹底することが大切です。
メニュー改善で他店との差別化を図る
「この店といえば」と思われる看板メニューを、原価率・提供時間・見た目の魅力で厳選し、メニュー表の右上に配置しましょう。メニューエンジニアリング(売上×粗利×出数によるABCD分類)を活用して商品構成を分析し、原価が上がったメニューはポーション・副材・価格の3点を調整して利益を守ります。
また、季節や地域の食材を活かした限定メニューで話題性を高めつつ、全体のコンセプトはぶれないように統一感を維持することが大切です。
FLコストや光熱費をこまめに見直す
原価率はレシピ原価表を用いて「基準 → 実測 → 差異」を定期的に確認し、実際のコストとのズレを把握します。食材ロスは週ごとに原因(過発注・仕込み過多・調理ミスなど)を分類し、仕入れ頻度や発注ロットを見直して最適化を図りましょう。
人件費は「来客予測 × 時間帯別ピーク」を基にシフトを設計し、仕込み作業はアイドルタイム(閑散時間)に集約して残業を抑制します。
また、光熱費対策としては、機器の待機電力カット、冷蔵庫内の詰め込み過ぎ防止、空調フィルターの定期清掃が基本です。さらに、省エネ機器の導入は補助金制度を活用し、投資と効果のバランスを見ながら段階的に進めるのが理想です。
働きやすい職場を作る
スタッフの定着率を高めることは、そのまま採用コストの削減につながります。シフトは早めに公開し、希望のヒアリングや急な欠員時の対応ルールを明文化しておくことが重要です。
評価制度は「接客・衛生・スピード・売上貢献」をスコア化し、結果を昇給や表彰で還元する仕組みを整えましょう。調理手順は写真や動画でマニュアル化し、セルフオーダーや自動釣銭機といった省力化設備を導入することで、現場の負担を軽減できます。
さらに、1on1ミーティングを月1回実施し、スタッフの悩みや不安を早期に把握・解消することが、働きやすい環境づくりと長期的な定着につながります。
他チャネルでの販路を開拓する
店内売上に頼らず、テイクアウト・デリバリー・冷凍・レトルト商品のEC販売・予約制コース・サブスク(ドリンクやランチパスなど)といった複数の収益源を持つことで、安定した経営を実現できます。
各チャネルごとに粗利率を把握し、手数料が発生する場合は価格設定に適切に反映させましょう。
新しいチャネルは、まず小規模からテスト的に始め、反応が良いものだけを拡大していくのがポイントです。また、雨の日限定のテイクアウト割引など、需要に合わせて柔軟に施策を打つことで、販売機会を逃さずに収益を伸ばすことができます。
地域のコミュニティと積極的に交わる
商店街や自治体、学校、近隣企業との連携を深め、イベント出店やコラボメニューなどを通じて地域での認知度を高めましょう。地元メディアへの情報提供や、SDGs・フードロス削減などの取り組みも発信素材として有効です。
SNSでは、地名・季節の行事・周辺スポットなどを絡めた投稿で「地域の話題」を継続的に発信します。地元とのつながりを感じさせる情報発信は、口コミや再来店の促進につながります。
キャッシュフローにも関わる!飲食店のゴミ処分の問題
飲食店経営において見落とされがちなのが「ゴミ処理」のコストと手間です。
飲食店から出るゴミは「事業系ゴミ」であり、家庭ゴミとは扱いがまったく異なります。多くの自治体では事業系ゴミを家庭ゴミの集積所に出すことは認められておらず、違反すると罰則の対象になる可能性もあります。
事業系ゴミは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。事業系一般廃棄物は生ごみや紙くずで、自治体の許可を得た業者に委託します。産業廃棄物は廃油や廃プラスチック類で、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託する必要があります。
重要なのは、ゴミ処理が単なる「出費」ではなく「食品ロスによる二重のコスト」だということです。売れ残った食材は、仕入れコストに加えて廃棄処理費用もかかります。適切な在庫管理と発注により食品ロスを最小限に抑えることがコスト削減につながります。
ゴミ処理業者を選ぶ際は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方に対応できるか、回収頻度と時間帯は適切か、料金体系は透明か、法令遵守(廃棄物処理法)のサポートがあるかを確認しましょう。
出典:e-GOV法令検索「https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137」
イーブライトに所属するゴミ回収ガールが、インスタグラムでゴミに関する情報を配信中!フォローやDMもお待ちしております!
まとめ
飲食店の廃業率は5.6%と全業種中最も高く、1年で約30%、3年で70%が廃業します。2024年の倒産件数は894件と過去最多を記録しました。
主な原因は運転資金の枯渇、初期投資の過大、人手不足、経営ノウハウの不足などですが、適切な準備と対策で回避可能です。生き残るためには、綿密な資金計画、立地選定、継続的なマーケティング、QSCの徹底、差別化、コスト管理、働きやすい職場づくり、多チャネル展開、地域との連携が重要です。
そして、ゴミ処理の適正化とコスト管理も持続可能な経営には欠かせません。
イーブライトでは、一般ゴミ・産廃ゴミの回収からグリストラップ清掃まで、飲食店の衛生環境を総合的にサポートしています。コスト削減や法令遵守の観点からも、ぜひ一度お問い合わせください。




