COLUMN コラム
飲食店の利益率は平均でどのくらい?計算方法や利益率アップのポイントを解説

飲食店を経営していると「売上は伸びているのに、なぜか手元にお金が残らない」と感じることはありませんか?売上だけを追いかけていても、実際に残る利益がわからなければ、経営の安定は望めません。
大切なのは「利益率」を正しく把握し、コントロールすることです。
本記事では、飲食店の利益率の相場から正しい計算方法、そして今日からできる具体的な改善策まで解説します。
飲食店の利益率はどのくらいが平均?
飲食店の利益率は、業態や規模によって異なりますが、まず業界全体の平均を知っておくことが重要です。経済産業省が公表している「商工業実態基本調査」によると、飲食業界全体の平均利益率は8.6%とされています。
この数値は、大企業を含めた業界全体の営業利益率です。実際には、多くの店舗がこの平均値前後で推移しています。
一方で、理想とされる利益率は10%から15%です。この範囲を目標として設定することで、健全な経営状態を維持しやすくなります。成功している飲食店のなかには、30%以上の高い利益率を達成しているケースもあります。
ただし、利益率が低いからといって、すぐに経営が立ち行かなくなるわけではありません。重要なのは、自店舗の利益率を正確に把握し、改善できる部分を見つけることです。
出典:経済産業省ウェブサイト「https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syokozi/result-2/h2c6klaj.html」
業種・業態別に見た小規模飲食店の利益率
飲食店といっても、業態によって利益率は大きく異なります。日本政策金融公庫が発表している「小企業の経営指標調査 飲食店・宿泊業」のデータを見てみましょう。
この調査では、実際に利益を上げている小規模飲食店(黒字かつ自己資本プラス企業)の売上高営業利益率が公開されています。いくつかの業態をピックアップすると、以下のような数値が報告されています。
食堂やレストランの黒字企業では、平均で4.9%程度の営業利益率となっています。一方、西洋料理店では7.7%と、やや高めの数値を示しています。バーや喫茶店も、それぞれの業態特性に応じた利益率で運営されています。
これらの数値は、実際に黒字化に成功している店舗のリアルな利益率です。自店舗のビジネスモデルと照らし合わせることで、現状が適正な水準にあるかを判断できます。
注意したいのは、ここで扱っているのはあくまで「営業利益率」という指標である点です。後ほど詳しく解説しますが、利益にはいくつかの種類があり、それぞれ意味が異なります。
業態によって理想とされる利益率が異なるため、同業他社のデータを参考にしながら、自店舗の目標を設定することが大切です。
出典:日本政策金融公庫ウェブサイト「https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/sme_findings2_08a.pdf」
こちらの記事では、飲食店開業の流れについて解説しています。
必要な手続きや提出書類も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
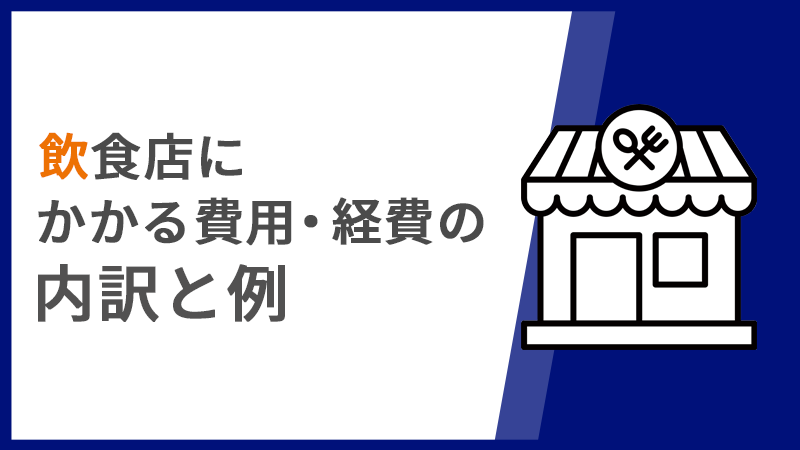
飲食店にかかる費用・経費の内訳と例
利益率を計算するには、まず飲食店にかかる費用・経費の全体像を理解する必要があります。経費は大きく分けて「固定費」と「変動費」の2種類があり、それぞれ性質が異なります。
これらの費用は、後ほど解説する営業利益の計算で使用する「販売費および一般管理費」を構成する要素です。経費の内訳を正しく把握することで、コスト削減策を考える際の判断材料となります。
固定費
固定費とは、売上の増減に関わらず一定額が発生する費用のことです。来客数が少ない日でも、満席になる日でも、同じ金額が必要になります。
代表的な固定費には、賃料(家賃・共益費)、正社員の人件費、光熱費の基本料金、設備のリース料、減価償却費、各種保険料などがあります。
固定費のなかでもとくに家賃は、最も大きな割合を占める重要な項目です。一度契約してしまうと削減が難しいため、出店計画の段階で慎重に決める必要があります。
理想的には、賃料や共益費を売上の7%から10%以内に抑え、レンタル機材の料金や支払利息、減価償却費を合わせて10%以下にすることが望ましいとされています。つまり、固定費全体では15%から25%の範囲内に収めることが目標です。
変動費
変動費とは、売上の増減に応じて変動する費用のことです。顧客が増えれば増加し、来客が少なければ減少します。
具体的には、食材費、アルバイトやパートの人件費、使用量に応じた光熱費、宣伝・広告費、消耗品費および雑費などが該当します。
変動費のなかでも、食材費と人件費はとくに大きな割合を占めます。この2つを合わせたものを「FLコスト」と呼び、飲食店経営において重要な管理指標となります。
変動費を削減する際には注意が必要です。極端にコストを抑えようとすると、サービスの質を落とす原因になります。たとえば、スタッフを減らしすぎて対応が遅くなったり、安い食材を使って料理の味が落ちたりすれば、顧客満足度の低下につながります。
変動費の管理では、質を維持しつつ効率化を図ることが重要です。また、消耗品費や雑費には、ゴミ処理費用も含まれる場合があります。見落としがちなコストですが、適切に管理すれば削減の余地がある項目です。
飲食店の利益率の計算方法
利益率を正しく計算することで、自店舗の経営状況を客観的に把握できます。ここでは、飲食店経営でとくに重要な「粗利益率」と「営業利益率」の計算方法を解説します。
粗利益率(粗利)の計算方法
粗利益率は、売上から売上原価(原材料費)を差し引いた割合を示す指標です。粗利益は「売上総利益」とも呼ばれ、商品の魅力度や価格設定の妥当性を測る初期の指標となります。
計算式は以下のとおりです。
粗利益(売上総利益)= 売上高 − 売上原価(原材料費)
粗利益率 = 粗利益 ÷ 売上高 × 100
たとえば、1皿1,000円のパスタを提供しており、原材料費が300円だった場合を考えてみましょう。
粗利益 = 1,000円 − 300円 = 700円
粗利益率 = 700円 ÷ 1,000円 × 100 = 70%
この場合、粗利益率は70%となります。粗利益率が高いほど、原材料のコストパフォーマンスがよいことを意味します。
ただし、粗利益には人件費や家賃などの諸経費が含まれていないため、手元に残る利益とは異なります。あくまで大まかな収益を示す数値です。
【補足】原価率も把握しておこう
粗利率の裏返しとなる指標が「原価率」です。原価率は、売上に対する原材料費の割合を示します。
原価率 = 売上原価(原材料費)÷ 売上高 × 100
先ほどのパスタの例では、原価率は以下のようになります。
原価率 = 300円 ÷ 1,000円 × 100 = 30%
飲食店の場合、原価率は30%程度が目安とされています。食材費(フードコスト)は変動費のなかでも最も管理しやすい要素のひとつです。
ただし、すべてのメニューを一律30%にする必要はありません。集客用の低利益メニューと、高収益メニューをバランスよく組み合わせることで、全体の原価率を適正に保つことが可能です。
営業利益率の計算方法
営業利益率は、本業の儲けを示す最も重要な指標です。粗利益から販売費および一般管理費(人件費、家賃、光熱費など)を差し引いて計算します。
営業利益 = 粗利益 − 販売費および一般管理費
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高 × 100
たとえば、月の売上高が500万円、原材料費が150万円、販売費および一般管理費が300万円の場合を見てみましょう。
まず粗利益を計算します。
粗利益 = 500万円 − 150万円 = 350万円
次に営業利益を計算します。
営業利益 = 350万円 − 300万円 = 50万円
最後に営業利益率を算出します。
営業利益率 = 50万円 ÷ 500万円 × 100 = 10%
この場合、営業利益率は10%となります。営業利益は、経営上で発生するコストを除いた手元に残る利益です。営業利益率が高いほど、本業の営業活動における収益力が高いと判断できます。
経営効率を測るためには、この営業利益率を定期的にチェックすることが不可欠です。
利益率の目標を考える際に必須の指標丨損益分岐点とFLコスト
利益率をさらに深く分析し、具体的な経営目標を設定するためには「損益分岐点」と「FLコスト」という2つの指標を理解する必要があります。
これらの指標を活用することで、赤字にならないための最低売上や、コスト管理の適正値を把握できます。
損益分岐点とは?
損益分岐点とは、売上と経費がちょうど等しくなる売上高のことです。別の言い方をすれば「赤字にも黒字にもならない売上高」を指します。
損益分岐点を超えれば黒字、下回れば赤字となるため、この数字を把握することが黒字経営の最低条件です。経営者としての危機管理意識を持つ上で、必ず知っておくべき指標といえます。
損益分岐点の計算方法
損益分岐点を計算するには、固定費と変動費を明確に分類する必要があります。
損益分岐点 = 固定費 ÷ (1 − 変動費 ÷ 売上高)
たとえば、月の売上高が300万円、固定費が60万円、変動費が150万円の店舗を考えてみましょう。
損益分岐点 = 60万円 ÷ (1 − 150万円 ÷ 300万円)
= 60万円 ÷ (1 − 0.5)
= 60万円 ÷ 0.5
= 120万円
この店舗の場合、月の売上が120万円を下回ると赤字になることがわかります。
計算式を見るとわかるとおり、損益分岐点を下げるには固定費を削減することが効果的です。仮に固定費が50万円になれば、損益分岐点は100万円まで下がります。
固定費の重さや粗利率の改善が、損益分岐点に直結することを理解しておきましょう。
FLコストとは?
FLコストとは、Food(食材費)とLabor(人件費)を合計した金額のことです。この2つは飲食店経営における最大のコスト要素であり、FL比率を管理することが利益率改善の鍵となります。
食材費も人件費も、売上に応じて変動する重要なコストです。FL比率を適切に管理することで、経営の健全性を保つことができます。
FL比率の計算方法
FL比率の計算式は以下のとおりです。
FLコスト = 食材費 + 人件費
FL比率 = FLコスト ÷ 売上高 × 100
たとえば、月の売上高が200万円、食材費が50万円、人件費が70万円(正社員40万円 + アルバイト30万円)の場合を見てみましょう。
FLコスト = 50万円 + 70万円 = 120万円
FL比率 = 120万円 ÷ 200万円 × 100 = 60%
一般的に、FL比率は55%から60%以内に抑えることが理想とされています。この範囲を超えると、利益を出すことが難しくなる状態です。
ただし、FL比率が低すぎてもよいとは限りません。食材費や人件費を過度に削減すれば、料理の質が低下したり、低賃金で人手不足につながったりします。
変動費をコントロールする重要性を認識しつつ、バランスの取れた経営を目指しましょう。
飲食店の利益率を上げるには?今日からできる8つの施策
これまで解説してきた分析を踏まえ、ここからは利益率を改善するための具体的な施策を紹介します。
食材費を抑える
食材費は変動費のなかでも大きな割合を占めるため、削減効果が高い項目です。ただし、質を落とさずにコストを下げる工夫が必要です。
まず検討したいのが、仕入先の見直しです。複数の業者から見積もりを取り、より安価で質のよい食材を調達できるルートを確保しましょう。業務用食材店への切り替えも選択肢のひとつです。
また、仕入れる量や取引期間に応じて、業者と価格交渉を行うことも有効です。長期的な取引を前提に、値引きを依頼してみましょう。
メニュー構成の見直しも重要です。原価の高い食材を使っているメニューについては、代替できる食材がないか検討します。ロスが出にくい食材を積極的に利用することで、廃棄コストも削減できます。
質を落とさずにコストを下げる交渉術を身につけることが、食材費削減の成功につながります。
人件費を抑える
人件費は売上の25%から30%が適正とされていますが、単純に削減すればよいというものではありません。人手不足でサービスの質が落ちては本末転倒です。
効果的なのは、人時売上高を活用した適正な人員配置です。人時売上高とは、スタッフ1人が1時間あたりに生み出す売上のことで、目安は4,000円~5,000円とされています。
この指標を参考に、時間帯ごとの来客数に合わせてシフトを最適化しましょう。ピークタイムには十分な人員を配置し、アイドルタイムには最小限の人数で回せる体制を作ります。
業務効率化と連動させることで、従業員の負担を増やさずにコストを抑えることが可能です。
光熱費を抑える
光熱費は比較的小さなコストですが、積み重ねで大きな差になります。省エネ設備の導入や、使用状況の見直しを行いましょう。
具体的には、LED照明への切り替え、エアコンの温度設定の見直し、調理機器の使用時間帯の管理などが挙げられます。営業時間外の電気の消し忘れにも注意が必要です。
水道光熱費の使用明細を定期的にチェックし、無駄がないか確認する習慣をつけましょう。
食品ロスを減らす
食品ロスの削減は、利益率改善において非常に重要な施策です。農林水産省の発表によると、令和4年度の日本の食品ロス推計1,525万トンのうち、99万トンが外食産業による廃棄とされています。
食品ロスを減らすことは「仕入れコスト」と「廃棄コスト」の二重の無駄を排除することにつながります。在庫管理を徹底し、適正な発注量を維持しましょう。
オーダーミスの削減も重要です。スタッフ間のコミュニケーションを改善し、厨房への伝達ミスを防ぐ仕組みを作りましょう。
出典:農林水産省ウェブサイト「https://www.maff.go.jp/hokkaido/asahikawa/attach/pdf/oensitai-11.pdf」
オペレーションを見直す
業務効率の向上は、人件費削減と回転率アップのどちらにも直結します。 限られたスタッフで売上を最大化するためには「無駄な動き」「重複作業」「属人化した工程」を徹底的に洗い出し、標準化・自動化していくことが欠かせません。
たとえば、セルフオーダーシステムやキャッシュレス決済の導入は、注文や会計にかかる時間を短縮し、ピークタイムの混雑緩和にもつながります。
また、調理工程の見直しも効果的です。仕込みの段取りを工夫したり、レシピや調理手順をマニュアル化したりすることで、提供時間を短縮し、味や品質のブレも防止可能です。結果として、顧客満足度の向上とリピート率アップにもつながります。
高利益メニューを増やす
飲食店の安定経営には、売上だけでなく利益率の高いメニュー構成が欠かせません。原価率が高い人気メニューばかりに頼ると、売上が伸びても利益が残らないという状況に陥りがちです。
とくにドリンクやサイドメニューは、原価率が低く利益につながりやすい傾向があります。新しいドリンクメニューの開発や、おつまみメニューの充実を検討してみましょう。
ただし、集客用の低利益メニューとのバランスも重要です。顧客を呼び込む目玉商品と、高収益商品を組み合わせることで、全体の利益率を適正に保つことができます。
高利益メニューを目立つところにアピールする
高利益メニューを考案したら、販促方法も工夫しましょう。メニューブックの配置を見直し、目立つ位置に掲載します。
具体的には、メニューを開いてすぐ目に入るページや、視線が集まりやすい右上の位置に配置すると効果的です。写真を大きく載せたり、おすすめマークをつけたりすることも有効です。
店内POPやスタッフによる声がけも、注文率を高める手段です。「本日のおすすめ」として積極的に紹介しましょう。客単価アップを促す仕組みづくりが、利益率向上につながります。
回転率を上げる
回転率を上げることで、同じ座席数でもより多くの売上を確保できます。とくにピークタイムのオペレーション改善に焦点を当てましょう。
まず注力すべきは、料理の提供スピードです。仕込み作業の段取りを改善し、調理工程を見直すことで、提供までの時間を短縮できます。実際に「注文から提供までの平均時間」を測定し、ボトルネックを明確にすることが重要です。
次に、会計の迅速化にも取り組みましょう。モバイルオーダーシステムやキャッシュレス決済を導入すれば、レジ待ち時間を削減でき、回転率だけでなく顧客満足度の向上にもつながります。
利益率にも関わる!飲食店のゴミ処分ルール
利益率改善の取り組みとして見落とされがちなのが、事業系ゴミの処理費用です。飲食店から出るゴミは家庭ゴミとは異なり、すべて「事業系ゴミ」として扱われます。
このうち、紙くずや生ゴミなどは「事業系一般廃棄物」、油や調理残渣、割れたガラスなどは「産業廃棄物」に分類されます。どちらも地域のゴミ集積所には出せず、行政の許可を受けた廃棄物処理業者に依頼する必要があります。
業者への依頼には当然コストがかかり、廃棄量が多いほど経費を圧迫します。とくに食品ロスは、仕入れ時点ですでにコストが発生しているうえ、廃棄にも処理費用がかかるため「二重の損失」を招く原因となります。
ゴミ処理は単なる義務ではなく、管理すべき経営課題のひとつです。仕入れや調理工程を工夫して食品ロスを削減するほか、分別の徹底やリサイクル化など、小さな改善を積み重ねることでコストを抑えられます。
さらに、廃棄物処理業者の選定も見直す価値があります。複数社から見積もりを取り、回収頻度や容器レンタル費用などを比較することで、無理のないコストで適正なサービスを受けられる体制を整えましょう。
出典:e-GOV法令検索「https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137」
イーブライトに所属するゴミ回収ガールが、インスタグラムでゴミに関する情報を配信中!フォローやDMもお待ちしております!
まとめ
飲食店の利益率は、業界平均で8.6%、理想的には10%~15%を目標とすることが一般的です。利益率を正しく把握し、FLコストや損益分岐点といった重要指標を管理することで、現状の課題を客観的に分析できます。
利益率を高めるには、食材費・人件費の最適化、食品ロスの削減、オペレーションの効率化など、複数の施策をバランスよく進めることが大切です。さらに見落とされがちな「事業系ゴミの処理費用」も、確実に管理すべき経費のひとつです。
事業系ゴミの収集・分別・リサイクルを手がけるイーブライトでは、計量器付きパッカー車を導入し、排出量を正確に管理しています。これにより、無駄のない収集体制を実現し、効率的な運用が可能です。
店舗の規模や営業形態に合わせて柔軟にプランを選べるため、ゴミ処理コストを削減しながら利益率を高めることができます。ご不明な点やご相談がある場合は、お気軽にお問い合わせください。




